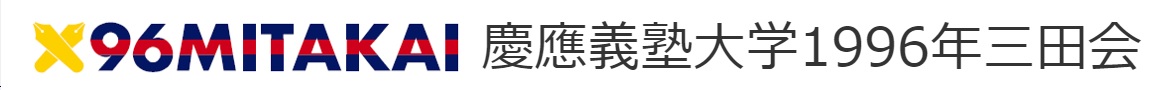私の履歴書 シリーズ16 津村 将子 :「映画を撮る目的は、人間とその営みの中で起こる悲しさ、痛み、美しさを伝えること。作ることは祈りのようなものでもあります」

津村将子(つむらまさこ)
慶應義塾大学環境情報学部卒業後、約20年前に夢を追って東京からニューヨークに移住。2003年にImakoko Media, Inc. を東京とニューヨークに設立し、インディペンデント映画製作を開始。写真家・荒木経惟のドキュメンタリー「アラキメンタリ」(2004)を編集、ホノルル映画祭でベスト編集賞、ブルックリン映画祭で観客賞を受賞。その後、33年間の拷問と投獄を生き抜いたチベット僧・パルデン・ギャツォの長編ドキュメンタリー映画を監督・プロデュースし、2008年にトライベッカ映画祭、IDFA、釜山映画祭など世界中の映画祭で公式上映後、ミラダス映画祭(スペイン)で審査員特別賞を受賞。2010年には日本全国のアートシアターでも劇場公開された。最近プロデュースしたドキュメンタリー映画「The Birth of Saké」はパームスプリング映画祭でベストドキュメンタリー映画賞を受賞したほか、アメリカの権威あるPBSチャンネルのPOVプログラムで放映され、世界中で数々の賞を受賞した。最近は長編劇映画作品Umiを製作準備しながら、短編ドキュメンタリー映画 「行き止まりのむこう側」を監督、プロデュース。イスラエル駐日大使館と共同製作し、今年2月のロッテルダム国際映画祭に正式出品されたこの作品は、東北大震災の津波で最愛の妻を失った高松康雄さんのストーリーをフューチャーし、自然の中に生きる人間の魂の並外れた回復力を描いている。
(インタビュアー 矢田貴子)
矢田:とってもご無沙汰です。中等部と女子高のイメージのままでビックリです。多くの同期が卒業後、大手企業に行く中、映画監督ってなかなか就かない職業ですね!どういう経緯でその職業を選んだのですか?
津村:もともと、10代のころからNYに住んでみたいと思っていたけれど、その思いがさらに膨らんだのは大学時代の経験があったからなんです。
学生時代は映画と建築に興味があり、特に前衛芸術グループ「ネオ・ダダイズム・オルガナイザーズ」の一員でもあった荒川修作氏が手がける前衛建築に惹かれ、大学最後の年には彼のもとでインターンとして働きました。彼の拠点がNYであったことから、私もNYに行ってみたい、住んでみたいという思いが深まり、大学卒業後、アルバイトをしてお金をためてからNYに引っ越したんです。
NYでは仕事をしながら、「30歳までに映画を撮りたい」という夢に向かって、映像系の専門学校で学び始めました。その後大学院に移り、そこで映像仲間と出会ったことで映画作りの楽しさにはまり、この業界に入っていくことになりました。
はじめは日本のテレビのコーディネーションやフィールドプロデュースからはじめ、アシスタント編集などを経て、プロデュースはオリジナルで「ザ・バース・オブ・サケ」という作品から行うようになりました。現在は主に、ドキュメンタリー映画のプロデューサー兼ディレクション(監督)を行っています。
矢田:すごい行動力ですね!なかなか周囲にいない職業なのに、チャレンジがすごいですね。ドキュメンタリーなど社会的な課題に即したテーマが多いんですか?
津村:メインはドキュメンタリー制作だけれど、コマーシャルの制作などもやりますね。
一般的な劇映画は、企画を作り、それをもって映画製作費を出してもらってから作り出すのが定石です。それに対してドキュメンタリー映画は、カメラさえあれば撮り始められる。だから「ザ・バース・オブ・サケ」(※)なんかは、日本でコマーシャルの仕事があるときについでに撮る、といったこともやっていました。
The Birth of Saké (https://www.birthofsake.com)
自分たちが気になるものや伝えたいものをまず撮って、良いフッテージ・素材が撮れたらそれを編集し、売り込みます。私たちはテレビ局に属しているわけではないから、資金集めも自分たちで行うんですが、これがかなり大変なパート。映画作りは、作るたびに「もう二度と作りたくない」と思うほどに大変な仕事ですね。
矢田:それでもやりたいという思いがあるから、次の作品、また次の作品と行くんですね。ご自身のお仕事での実現したいこと、目的はなんなのでしょうか?
津村:映画を撮る目的は、人間とその営みの中で起こる悲しさ、痛み、美しさを伝えることです。それを伝えたい、という強い思いが私たちにはあり、作ることは祈りのようなものでもあります。例えば最近公開した「行き止まりのむこう側」(※)という短編映画は、東日本大震災についての物語で、女川で津波に飲み込まれて行方不明になった妻の遺体を捜すため、海に潜り続ける高松康雄さんについてのドキュメンタリー映画です。この短編は、やはり同じ高松さんのストーリーを基盤にして脚本を書き、4年半かけて撮影準備と資金集めをしているUmiという長編劇映画から派生しました。
行き止まりのむこう側 (https://www.nowheretogobuteverywhere.com)
私が今、撮りたいと思っている映画は、女性についての物語。日本企業と仕事をしていると特に、家父長制度が社会の構造自体に影響を与えていることを実感することがとても多いです。アメリカでも、日本ほどではないにせよ、ジェンダーにおける非対称性や、女性であるが故の生きにくさを感じるシーンは存在します。みなさんから「自由」「公平」「平等」のイメージが強いアメリカですら、ですよ。家父長制というものは、国に関係なく、世界規模で偏在する構造と考えています。
この企画はCOVID-19の影響で頓挫してしまっていますが、いつか必ず撮らなければいけないと感じ続けています。
矢田:ライフワークとしてのテーマがあるんですね!私も卒業後ずっと働いていますし、どちらかと言えば気にしない方ですが、確かにそういう場面にも遭遇します。令和なのに、と思うこともありますよね。
それでは最後に、慶應義塾とのつながりをお伺いしたいと思います。津村さんにとっての慶應義塾とはと言われると??
津村:実は、NYで仕事していると誰も慶應義塾大学なんて知らないんですよね。笑。その意味では、けっきょく大切なのは学歴ではなく、どういう人間なのか、何ができるのかに尽きると考えています。広い世界の視野で見ると、私たちの学校の存在はとても大きいわけではないです。
とはいえ、久しぶりに話してもすぐ意気投合することができるのは、慶應義塾で同じ時を過ごしたという共通の体験があるおかげだと感じます。それは、受けた教育、過ごした環境が、同じ経験を通じて、共通のコミュニケーションを作るのではないかと思います。アイディアが欲しいときや相談に乗ってほしいときに頼りになる仲間がいると感じられるのは、貴重な財産と言ってよいと思います。
矢田:本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます!また、映画を通じて津村さんを感じられたらいいなと思います!